

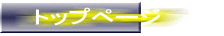 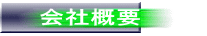 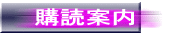 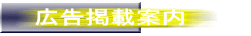 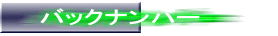 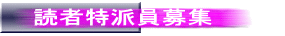  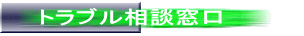   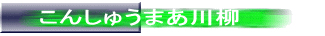 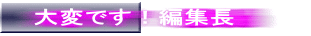 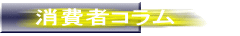 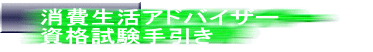   https://syohi.com/oocfile/     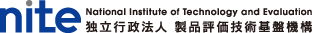  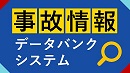  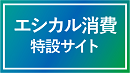     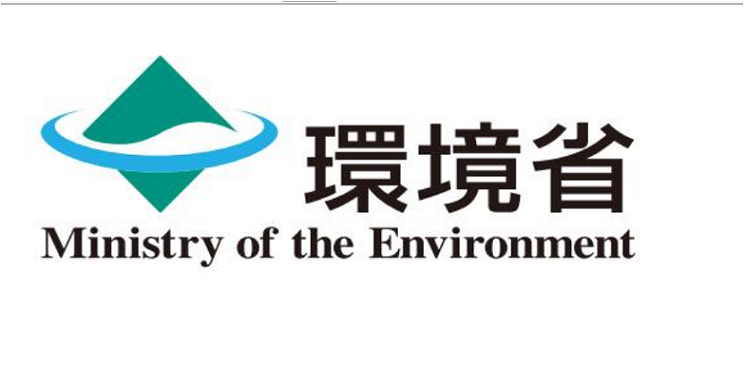  「消費と生活」はオンラインでも紙媒体・電子ブックの購読の申し込みができます。
|
消費者総合雑誌「消費と生活」は昭和41年(1966年)創刊。2025年10月、59周年を迎えました。
|
||
|
<グラビア>
日本消費者教育学会全国大会/「ハッピーセット」問題で消費者庁長官が要望/10月18日「冷凍食品の日」イベント/インターナショナル・ギフトショー秋/鮮度の良い魚を焼き肉スタイルで提供 <特集> 消費者の点検が製品の安全性を守る重要要因 編集部 知って得する!「自分で点検」(一般社団法人リビングアメニティ協会) 11月は「製品安全総点検月間」(一般財団法人家電製品協会) 電気製品の安全・安心の「Sマーク」(電気製品認証協議会SCEA) 消費者が安全点検を行い石油暖房機を安全に使おう(一般社団法人日本ガス石油機器工業会) <連載> やぶにらみ社会学 264 ぼっちのアリ 足立則夫 消費者側の対策にも限界がみえる代引きトラブル 多田文明 特殊詐欺の被害が増加、その傾向と対策 深山智理 消費者センターめぐり 246 千歳市消費生活センター 消費者問題なう ハッピーセット 猪瀬 聖 <消費者情報> 新型コロナ感染の消費行動の変化/高齢者の方が食品ロスの関心が高い/ACAPがマニュアル方針、AI対応を学ぶ講演会開催/国民生活センター、全国の危害・危険情報の状況公表/NACSが「水際検疫」の役割と現状を考える公開講座/?好アジア旅游商大会2025 映画「アバター」の世界を堪能 <商品特集> 食事にもおやつにも 栄養豊富なチーズを食べて元気に過ごそう! コンシューマー・アイ 我が家の環境問題・再エネ取り組み 柴田直三 日常的な自分へのご褒美スイーツ この秋のおいしいチョコレート <話題> 大さじ1杯で1人前 顆粒だし鍋つゆ(シマヤ) 感謝の気持ちや愛情を冬のギフトに託して贈りたい 下味冷凍用おかずの素「パッとジュッと」シリーズ(理研ビタミン) ガスと電気のコンパクトなハイブリッド給湯器(パロマ) 毎年10月はLPガス消費者保安月間 その精度も検定が支える(日本電気計器検定所) 「高年齢労働者の安全と健康確保」強調月間(ミドリ安全) 秋を彩るメニューレシピ 暮らしの商品情報 親子で一緒に使ってお揃い美髪/ツインエンジン構造オーブンレンジ/奥行うす型60cm コンパクトな冷蔵庫/「バンテリンコーワ」から温感パッチ剤新発売/口腔内環境を整え歯周病予防&知覚過敏ケア/世代や性別を超えたエイジング スキンケア cinema 11月・12月公開の作品 BOOKSTALL 読者のひろば 羅針盤・編集後記 羅針盤(消費と生活のコラム)認知症大国時代厚生労働省が公表した2025年時点の認知症の人は65歳以上のうち471万人(12.9%)。軽度認知障害のMCIの人は2022年時点で558万人(15.5%)だった。認知症の人の割合は65歳から69歳で1.1%なのだが、85歳以上では3割超に。85歳から89歳の男性が25.2%、女性が大きく上回って37.2%だった。 この差はどこに原因があるのか今後の研究を待ちたい。 認知症は、2040年には584万人(14.9%)、2060年には645万人(17.7%)で同5.4ポイント増を見込む。65歳以上のうちおよそ6人に1人となるという。 MCIの人の将来推計も初めて出されたが、2040年に612万人(15.6%)、2060年に632万人(17.4%)と推計され、認知症の人とあわせると、およそ3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになる。 認知症やMCIの人の数が増えるのは、高齢人口が増えるので仕方ないが割合が増える予測なのはなぜだろう。 核家族化や高齢化が進んだことで、一人暮らしをする65歳以上の認知症高齢者の数は増加傾向にあり、2025年には約121万人、2040年には約168万人に達すると予測されており、それも一 因なのかもしれない。また、他国に比べ認知症が多いのは、高齢期の貧困問題もかかわっていると指摘する人もいる。 認知症は、面倒を看る親のこと、自分自身のこととして関心の高いことだが、予防の手はあるのだろうか? 多くの医師が指摘するのは、仕事や生きがいを持つこと。認知症の引き金になる脳梗塞などの病気にならないために食事や運動、生活習慣の改善を推奨する。定年後、少しはのんびりしたいと何もしない人はリスクも抱えるということだろう。 認知症にならないために働き、収入を得る努力をすることは、経済問題の解決もするだろう。高齢期の人が安心して働ける環境を整えていくことも認知症を減少する対策になるのではないだろうか。 |